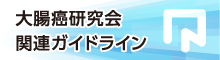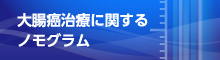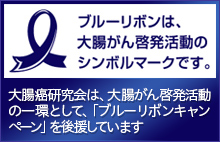はじめに
この度「大腸癌治療ガイドライン医師用2024年版」を刊行しました。2022年版ではJCOGで行われた二つの第Ⅲ相試験の結果とMSI-H大腸癌やBRAF遺伝子異常大腸癌に対して有効な薬剤が登場したことをもとにした部分改訂でしたが,今回は,大腸癌の治療にかかわるすべての領域(内視鏡治療領域,外科治療領域,薬物療法領域,放射線療法領域)の改訂と,CQを刷新したこと,資料を刷新したことが主な変更点です。
近年,直腸癌治療においてTotal Neoadjuvant Therapy(TNT)や,Non-Operative Management(NOM,Watch and Wait療法)が欧米を中心に行われるようになっており,国内からの報告も増加していますが,直腸癌治療の背景が欧米と大きく異なる本邦における位置付けは不明で,引き続き重要な検討課題となります。一方で,新たな薬物療法の登場や,切除困難な直腸癌術後局所再発に対する粒子線治療が保険適用になったことは,患者さんにとっても医療者にとっても朗報です。
さらに,資料の一部が刷新されました。大腸癌研究会の全国登録のデータを用いて2008~2013年に手術が行われた大腸癌の部位別・壁深達度別リンパ節転移頻度,Stage別治癒切除率,部位別5年生存率,同時性遠隔転移頻度,が「大腸癌取扱い規約第9版」に準拠して記載されています。2019年版では「大腸癌取扱い規約第8版」に沿って記載されていましたが,規約第9版では第8版と比べ,リンパ節転移,遠隔転移,進行度の分類に大きな変更があったことから,全国登録委員会に依頼して第9版に準拠したデータとして作成してもらいました。これを用いて,患者さんへの説明や英文論文作成の際の資料として役立てることができると思います。
これまでの本ガイドラインの根幹である「エビデンスはあくまでも治療法を選択する際の判断材料の一つであり,ガイドライン作成の際はエビデンスを中心にすえながら,医療環境,治療法の難易,利益と不利益のバランス,患者さんの状態,などを考慮しながら専門医たちが合意のうえ推奨度を決める」ことを踏襲し,本改訂作業においては,委員のvoting結果も分かるようにして,委員内での意見の相違等も透明性を持って分かるようにする(合意率の記載),補助療法に関しては,関連領域が合同で原案作成,推奨度の決定を行ったことが,大きな変更点となります。特にCQに取り上げられるような治療方針は,専門家でも意見が分かれることを理解し,臨床現場では,その推奨度とエビデンスを参考にしながら,患者さんの健康状態・考え・環境,医療費,交通の便などを考慮して,患者さんとその家族とともに治療法を決めるのが基本だと思います。
2024年1月25日
大腸癌研究会会長
味岡 洋一