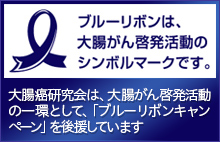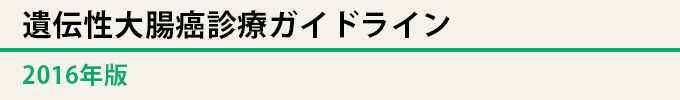
Clinical Questions
CQ2:Attenuated FAP(AFAP)の治療において注意すべき点は?
CQ3:FAPに対する術式(予防的大腸切除術)を選択する際のポイントは?
CQ4:FAPに対する大腸全摘・回腸囊肛門(管)吻合術(IPAA)において一時的回腸人工肛門造設の必要性は?
CQ5:FAPの大腸癌に対する予防的大腸切除が推奨される年齢は?
CQ6:FAPに対する腹腔鏡下手術は有用か?
CQ7:大腸全摘・回腸囊肛門(管)吻合術(IPAA)は女性FAP患者の妊孕性,妊娠,出産に悪影響があるか?
CQ8:FAPの腺腫に有効な薬物療法はあるか?
CQ9:結腸全摘・回腸直腸吻合術(IRA)後の直腸癌の発生リスクにはどのように対応するか?
CQ10:FAPの胃病変にはどのように対応するのか?
CQ11:FAPの十二指腸腺腫(乳頭部を除く)にはどのように対応するのか?
CQ12:FAP患者の十二指腸乳頭部腫瘍(腺腫・癌)にはどのように対応するのか?
CQ13:FAPの空・回腸病変にはどのように対応するのか?
CQ14:FAP患者のデスモイド腫瘍の治療方針は?
CQ15:FAP患者において注意すべき消化管以外の悪性腫瘍は?
CQ16:FAPの遺伝カウンセリングの注意点は?
CQ17:リンチ症候群では原因遺伝子の種類によって関連腫瘍に対し異なる対応が必要か?
CQ18:大腸癌の病理組織学的所見のなかで,リンチ症候群の拾い上げに重要なものは何か?
CQ19:リンチ症候群(大腸癌未発症の変異保持者を含む)において,婦人科癌にどのように対応するか?
CQ20:リンチ症候群のスクリーニング検査(MSI検査と免疫染色)において,どのような点に注意するのか?
CQ21:ミスマッチ修復遺伝子産物(タンパク)の免疫染色における評価ポイントは?
CQ22:リンチ症候群の遺伝子診断の意義と注意点は?
CQ23:リンチ症候群の遺伝学的検査における「病的か意義不明なバリアント」(variant of uncertain significance:VUS)にはどのように対応したらよいか?
CQ24:リンチ症候群の遺伝カウンセリングを行う際のポイントは?
CQ25:リンチ症候群の大腸癌に対する術式選択は?
CQ26-1:リンチ症候群の大腸癌に対する有効な補助化学療法は?
CQ26-2:リンチ症候群の進行・再発大腸癌に対する有効な化学療法の選択は?
CQ27:リンチ症候群の発がんに対する有効な生活習慣の改善策は?
CQ28:リンチ症候群の発がんに対する有効な化学予防の方法は?
CQ29:リンチ症候群の患者に対する大腸内視鏡によるサーベイランスは有効か?
CQ1:FAPの診断・治療において遺伝学的検査が必要な場合は?
以下の場合,APC遺伝子の遺伝学的検査が必要である。
(1)臨床的にFAPと診断された患者に対し,治療法の選択やサーベイランスの参考にする
(2)APC遺伝子変異が判明している家系において,患者の血縁者が検査を希望する
(3)AFAPの診断やMUTYH関連ポリポーシス,ポリメラーゼ校正関連ポリポーシスとの鑑別診断
1.臨床的にFAPと診断されている患者に対する遺伝学的検査
FAPの診断は家族歴がない場合でも臨床的に診断可能な場合が多い。しかしながら,APC遺伝子の変異の部位(遺伝子型)と大腸腺腫数やその他の随伴病変など(表現型)との関連が認められており,治療法の選択やサーベイランスの参考になる場合がある。
2.APC遺伝子変異が判明している患者の血縁者に対する遺伝学的検査
APC遺伝子変異が判明している患者の血縁者(例えば患者の子供)を対象に,FAPの診断が可能になる。
3.AFAPの診断あるいはMUTYH関連ポリポーシスとの鑑別
AFAPではポリープ数が100個未満,常染色体優性遺伝に矛盾しない家族歴,随伴病変などから臨床診断は可能なことが多いが,APC遺伝子変異の同定は確定診断となる。患者のみ,あるいは兄弟姉妹のみに100個未満の大腸腺腫が認められる場合には,MUTYH関連ポリポーシスの可能性があり,APC遺伝子の遺伝学的検査の後または同時にMUTYH遺伝子の遺伝学的検査を行うと両者の鑑別に有用である。MUTYH関連ポリポーシスは常染色体劣性遺伝形式であり,血縁者のリスク評価やサーベイランスなどを考えると,いずれの遺伝子変異によるものかを明らかにすることは重要である。
臨床的にFAPと診断されてもAPC遺伝子変異が検出されない場合がある。欧米からの報告では,通常の検査方法でAPC遺伝子変異が検出されるのは古典的(典型的)FAPの約60%であり,20~99個の大腸腺腫を認める患者では,10%にAPC遺伝子変異,7%に両アレルのMUTYH遺伝子変異を認め,10~19個の患者では,それぞれ5%と4%である。APC遺伝子変異が検出できない理由としては,①使用した解析法では検出できないようなAPC遺伝子の異常,②未知の大腸ポリポーシスの原因遺伝子の存在,③APCモザイク,④MUTYH関連ポリポーシス,⑤ポリメラーゼ校正関連ポリポーシスなどが考えられる。
遺伝学的検査を行う場合は,日本医学会の「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」や遺伝関連学会のガイドラインなどを遵守することが原則である。これらの遺伝学的検査は保険収載されていないが,APC遺伝子の遺伝学的検査は検査会社に依頼して実施することができる。検査には2~3 mL程度の全血が必要である。
CQ2:Attenuated FAP(AFAP)の治療において注意すべき点は?
AFAPでは結腸全摘・回腸直腸吻合術(IRA)や大腸内視鏡検査による長期的なサーベイランスも考慮される。
大腸の腺腫数(100個未満)だけから直ちにAFAPと診断することは困難だが,FAPの家族歴,FAPないしAFAPに随伴する可能性のある胃底腺ポリポーシス,十二指腸腺腫,外(潜在)骨腫,デスモイド腫瘍あるいは先天性網膜色素上皮肥大などが補助診断として参考になる。
上記のような特徴が明らかでない場合は,MUTYH関連ポリポーシスやポリメラーゼ校正関連ポリポーシスと鑑別することは困難で,確定診断には遺伝学的検査が必要である。
AFAPに認められるAPC遺伝子変異は,APC遺伝子の5′側や3′側の領域のほかに選択的スプライシング領域(変異により特定のexonが転写時に読み飛ばされる領域)などに認められるが,遺伝子変異が同定されない場合も多い。
AFAPは典型的FAPに比べて大腸癌発生平均年齢が高い。Burtらが調査した2家系120症例では,AFAPの診断時平均年齢は41歳であり,大腸腺腫数はさまざまで平均25(0~470)個であった。大腸癌発生年齢は平均58(21~81)歳で,75%は右側結腸に存在した。80歳までの累積大腸癌発生率は69%と,典型的FAP(ほぼ100%)に比べ低かった。大腸癌研究会の多施設共同研究によれば,AFAPの大腸癌発生年齢は平均50歳で,55歳までに半数が大腸癌を発症していたが,典型的FAPと比較すると高齢であった。したがって,AFAPでは直腸癌を合併していなければ,IRAや内視鏡治療による長期経過観察も選択肢となる。
CQ3:FAPに対する術式(予防的大腸切除術)を選択する際のポイントは?
大腸全摘・回腸囊肛門(管)吻合術(IPAA)が標準的術式である。非密生型や直腸に腺腫が少ない患者には結腸全摘・回腸直腸吻合術(IRA)も選択肢となる。
典型的FAPでは,IPAAが標準的な術式である(図13)。回腸囊には一般的にJ型が用いられることが多い。直腸粘膜を歯状線から切除して回腸囊と歯状線を手縫いで吻合する回腸囊肛門吻合術(hand-sewn IPAA)と,外科的肛門管と回腸囊を器械吻合する回腸囊肛門管吻合術(stapled IPAA)とに大別される。前者の方が直腸粘膜の残存は少ないが,術者の熟練を要する。大腸癌研究会の多施設共同研究の結果では,近年本邦における腹腔鏡下手術の割合が70%を越え,hand-sewn IPAAが選択される割合も多くなっている。(CQ6)
AFAPではIRAが推奨される。AFAP以外にIRAが考慮されるのは,非密生型で直腸腺腫数が20個未満かつ最大径10 mm未満の場合,若年女性で妊娠を希望するもの,就学・就職前の若年者などである。IPAAとIRAを比較したメタアナリシスでは,排便回数,夜間排便,パッドの使用についてはIRAの方がすぐれていたが,便意切迫(fecal urgency)についてはIPAAの方がすぐれていた。術後合併症(30日以内)はIPAAの方が有意に高かった(23.4% vs. 11.6%)。術後性機能,食事制限,長期合併症,デスモイド腫瘍発生率については,IPAAとIRAの間で差がなかった。IPAA後の合併症は手術チームの経験が増すとともに低下することが報告されている。
腸間膜デスモイド腫瘍を合併する症例ではIPAAは困難な場合が多くIRAが選択されることが多いが,回腸囊が骨盤底まで届けばIPAAを行ってもよいとする見解もある。
肛門温存術が普及する以前に行われていた大腸全摘・回腸人工肛門造設術は,予防的大腸切除の目的で施行されることはほとんどない。大腸癌研究会の多施設共同研究では,大腸癌を含む解析結果でも全体の約3%に施行されていたに過ぎない。進行下部直腸癌合併症例,肛門機能が不良な症例や回腸囊が骨盤底まで届かない症例などに限定して行われる。
大腸癌を合併する症例では,癌の進行度,部位を考慮して総合的に術式を決定する(各論③ 治療 2)大腸癌の治療を参照)。
CQ4:FAPに対する大腸全摘・回腸囊肛門(管)吻合術(IPAA)において一時的回腸人工肛門造設の必要性は?
全例に一時的回腸人工肛門を造設する必要はないが,造設するメリットとデメリットのバランスを考慮して個別に対応する。
IPAAに関する最近のメタアナリシスによると,一時的回腸人工肛門造設群は非造設群より縫合不全は少ないものの,吻合部狭窄,腸閉塞が多いことが報告されている。一時的回腸人工肛門の造設を回避できる条件として,①器械吻合(stapled IPAA)である,②吻合部に緊張がかかっていない,③完全に吻合が行われた,④十分な止血が得られた,⑤吻合部からの空気の漏れがない,⑥栄養失調や感染,貧血,ステロイドの常用がない,などが挙げられている。IPAA後に縫合不全が生じると,長期的合併症としてpouch failureが生じる可能性がある。このpouch failureの原因として,肛門機能障害と回腸囊の拡張不良が挙げられている。このような観点から,IPAA術後の縫合不全や骨盤内膿瘍が生じても,なるべく軽微な状態に抑えるために,一時的回腸人工肛門を造設することは有用と考えられる。ただし,以上の報告は潰瘍性大腸炎とFAPの症例を合わせた報告であり,その内訳でもFAPの割合は少ないことに注意が必要である。
FAPのみを対象にしたIPAAの報告では,一部のstapled IPAAを除き,ほとんどの症例で一時的回腸人工肛門が造設されていた。20歳未満のFAP患者に対し一時的回腸人工肛門造設の有用性を検討した報告によると,一時的回腸人工肛門非造設例は長期的な排便コントロールは良好であるが,術後30日以内の縫合不全率は一時的回腸人工肛門造設例と比べて有意に高く(17.2% vs. 0%,p=0.002),再手術率も高かった(20.7% vs. 4.6%,p=0.02)。ただし,対象のほとんどがstapled IPAAであり,hand-sewn IPAAにおける一時的回腸人工肛門造設についてはさらなる検討が必要である。
大腸癌研究会の多施設共同研究において,IPAAの際に一時的回腸人工肛門が造設されたのは55%であった。
一時的回腸人工肛門造設術後の人工肛門閉鎖術に関するシステマティック・レビユーでは,人工肛門閉鎖術は安全であるが,腸閉塞を7.6%(再手術は全体の2.9%),縫合不全を2.0%,創部感染を4.0%,晩期合併症としてヘルニアを1.9%,腸閉塞を9.4%に認めるなど全体の16.5%に合併症を認めた。
以上を勘案すると,選択されたFAP症例に対し,IPAA時に一時的人工肛門造設を回避することは可能であるが,その適応基準を決定するのは容易ではない。したがって,一時的人工肛門造設のメリット,デメリットのバランスを考慮した上で,個別に対応するのが現実的である。
CQ5:FAPの大腸癌に対する予防的大腸切除が推奨される年齢は?
一般に20歳代で手術を受けることが多いが,性別,大腸腺腫の密度,癌化の有無,随伴病変のほかに患者の社会的背景などを総合的に考慮した上で決定する。
予防的大腸切除の時期については,①累積大腸癌有病率,②腺腫密度,③腺腫の大きさと形態,④その家系員の死亡年齢,癌発生年齢,およびデスモイド腫瘍発生状況,⑤APC遺伝子変異部位,⑥患者の就学,就職などの環境,⑦回腸囊肛門(管)吻合術後の妊孕性や男性性機能障害,⑧下痢,腹痛,下血などの消化管症状,および⑨腫瘍の病理組織所見,などを総合的に考慮して決定する。大腸癌の有病率の点から,典型的FAPでは早ければ10歳代後期から,多くは20歳代に手術を受けることが推奨されている。
大腸癌研究会の多施設共同研究によると,累積大腸癌(粘膜内癌を除く)発生率は20歳で1%程度であるが,30歳になるとAFAPで9.6%,典型的FAPで21.4%と増加し,典型的FAPの方が発生率が高い(資料:Ⅰ.家族性大腸腺腫症 資料表3:大腸癌と十二指腸腺腫の累積発生率)。
CQ6:FAPに対する腹腔鏡下手術は有用か?
FAPに対する腹腔鏡下手術は,施設の習熟度に応じて十分なインフォームド・コンセントのもと適応を決定する。
近年,予防的大腸切除の術式として大腸全摘・回腸囊肛門(管)吻合術(IPAA)も結腸全摘・回腸直腸吻合術(IRA)も,ともに腹腔鏡下手術の割合が増加している(IPAA:23~53%,IRA:58~62%,)。これまでの研究では,腹腔鏡下手術では手術時間が長いものの,術後合併症率,死亡率,再手術率,再入院率には差はなく,整容性に優れ術中出血量も少なかった。また,腹腔内の癒着が少ないことから,術後腸閉塞も少なく,さらに女性では術後妊孕性の低下が少ないとの報告もある。大腸癌研究会の多施設共同研究によれば,近年の腹腔鏡下手術の割合は70%を超え,IPAAの171例中74例(43%),IRAの85例中52例(61%)に腹腔鏡下手術が行われていた。
腹腔鏡下手術の手術時間は長いものの短期成績を含む安全性は担保されており,本疾患に対する腹腔鏡下手術は施設の習熟度(腹腔鏡下手術および本疾患に対する理解)に応じて十分なインフォームド・コンセントのもとに適応を決定する。
CQ7:大腸全摘・回腸囊肛門(管)吻合術(IPAA)は女性FAP患者の妊孕性,妊娠,出産に悪影響があるか?
IPAA後には妊孕性が低下する可能性があるが,妊娠経過と分娩への悪影響は少ない。
デンマークの女性FAP患者58名を対象とした研究では,妊孕性は90%で,一般集団と同等であった。162名のヨーロッパの女性FAP患者を対象とした研究では,手術を受けていないFAP患者の妊孕性は一般集団と同等であった。また,IRAを受けた患者の妊孕性も一般集団と同等であったが,IPAAを受けた患者では妊孕率が0.46倍に低下していた。一方,オランダのFAP患者138例を対象とした研究では,妊孕性は術式とは関連がなく,初回手術の年齢と関連があることが報告されている。
IPAA後の妊孕性低下の原因としては,術後の癒着が考えられている。Oreslandらは大腸全摘後に子宮・卵管造影を行い,卵管の骨盤壁への癒着を48%に,片側閉塞を43%に,両側閉塞を10%に認めたと報告している。
FAPと潰瘍性大腸炎の患者を含めた検討では,腹腔鏡によるIPAAは,開腹手術よりも妊孕性が有意に高かったという報告されている。しかし,FAP患者を対象とした前向きの検討はない。
FAPと潰瘍性大腸炎の患者を含めた検討では,IPAA後の妊娠・経腟分娩は安全であることが報告されている。ただし,IPAA後の経腟分娩では会陰切開後の肛門括約筋の損傷と骨盤底筋の神経損傷を考慮しなくてはならない。
CQ8:FAPの腺腫に有効な薬物療法はあるか?
NSAIDsが大腸腺腫や十二指腸腺腫に対して試みられている。腺腫の個数を減少させたとする報告は多いが,腺腫の新たな発生についての有用性は明らかでない。
FAPの大腸腺腫に対し,NSAIDsの一つであるsulindacの効果が数多く検討されてきた。Sulindac(150~300 mg/日)の6週間から98カ月間の投与は大腸腺腫,ないしは結腸全摘術後の直腸腺腫の個数を50%以上減少させたが,150~300 mg/日の2年間の投与は腺腫の新たな発生を抑制しなかった。
選択的Cox-2(cyclooxygenase-2)抑制薬の一つであるcelecoxibの高用量(800 mg/日),6カ月投与はFAPの大腸腺腫の個数を28%減少させた。CelecoxibをFAP患者の腺腫の抑制に使用するには高用量を長期間投与する必要がある。選択的Cox-2抑制薬の一つであるrofecoxibも結腸全摘術後の直腸腺腫の個数を7%程度減少させることが報告されたが,rofecoxibの長期使用は心血管系の有害事象が多く,腺腫の予防ないし治療的投与は推奨されない。
現在のところ,大腸腺腫や十二指腸腺腫の新たな発生を抑制する有用な薬物療法の報告はない。
CQ9:結腸全摘・回腸直腸吻合術(IRA)後の直腸癌の発生リスクにはどのように対応するか?
残存直腸の癌発生に対する長期間のサーベイランスが必要である。
IRA後の長期観察では24~43%に残存直腸に癌が発生する。IRA後20年までの経過で直腸を切除する必要があったのは,AFAPで10%,非密生型FAPで39%,密生型FAPで61%であった。
外科技術の進歩とともにIPAAの割合が多くなっていること,直腸癌の危険因子をより多く持つ症例にIPAAが選択されることにより,IRA後の直腸切除率も40%から13%に減少し,IRA後の残存直腸癌の累積発生率も減少している。
CQ10:FAPの胃病変にはどのように対応するのか?
東アジアのFAP患者では一般集団に比べ胃癌のリスクが高く,長期にわたる内視鏡によるサーベイランスが必要である。
FAP患者の約50%に胃底部から胃体部にかけて隆起型ポリープが多発する(胃底腺ポリポーシス)。胃底腺ポリポーシスを背景とした腺窩上皮型腫瘍(WHO分類のfoveolar-type adenoma)や幽門腺腺腫の発生が知られており,まれではあるが浸潤癌の発生も報告されている。特に集合した大きなポリープでは異型あるいは癌化が認められるので内視鏡的切除の適応となる。胃底腺ポリポーシスに対する胃切除は行わない。幽門前庭部には単発あるいは散在性に陥凹型あるいは隆起型の腺腫が発生する。以上より癌化のリスクも考慮し,1 cm以上の腺腫はFAPに伴わない散発性の腺腫と同様に内視鏡的摘除の相対適応である。FAPの胃癌発生率は,欧米では一般集団と同等であるが,東アジアでは一般集団の3~7倍と報告されている。年1回(あるいは十二指腸腺腫のサーベイランスと同時)の上部消化管内視鏡検査を行うことが望ましい。
CQ11:FAPの十二指腸腺腫(乳頭部を除く)にはどのように対応するのか?
十二指腸腺腫に対する治療法・サーベイランスについてコンセンサスは得られていないが,スピゲルマン(Spigelman)の病期分類を参考にする。
FAPの死因の大部分(61~69%)を占める大腸癌を除くと,十二指腸(乳頭部を含む)癌はデスモイド腫瘍に次いで多く,FAP患者の死因の約3%を占める。FAP患者の十二指腸癌の一般集団に対する相対リスクは250~330.8倍である。十二指腸癌の累積発生率は57歳で4.5%程度と考えられている。十二指腸腺腫はFAP患者の30~90%に認められ,腺腫有病率は40歳を過ぎると高くなり,最終的には90%に達する。十二指腸腺腫の発育はきわめて緩徐だが,定期的内視鏡サーベイランス・治療が必要である。大腸癌研究会の多施設共同研究によれば,十二指腸腺腫の50歳までの累積発生率は39.2%で,典型的FAPはAFAPと比較して有意に累積発生率が高かった(42.5% vs. 23.5%)。十二指腸腺腫の臨床病理学的分類としてスピゲルマン(Spigelman)の分類がある。スピゲルマン分類は,内視鏡検査で十二指腸腺腫の個数,最大径を評価し,さらに腺腫の生検組織像(図14)について,組織構造と異型度を評価する。現在では若干の修正(修正スピゲルマン分類)が加えられている(サイドメモ6:スピゲルマン分類の評価法の変遷)。
十二指腸腺腫の診断には,直視内視鏡,斜視内視鏡を用いる。オランダでのFAP患者37例を対象とした研究では狭帯域光観察(narrow-band imaging:NBI)の使用により十二指腸腺腫の同定数は増えたが,スピゲルマン病期分類には影響を与えなかった。
十二指腸腺腫に対する内視鏡的治療にはスネアによる摘除,焼灼,アルゴンプラズマ凝固などがある。スピゲルマン病期Ⅰ/Ⅱに分類される腺腫では内視鏡的焼灼が選択される。腺腫数が多い場合,内視鏡的あるいは十二指腸切開による切除では不十分な対応となる。スピゲルマン病期Ⅱ/Ⅲに対する内視鏡的完全摘除は合併症が多く,50~100%の再発率が報告されている。FAP患者の十二指腸病変に対し,内視鏡的治療と経過観察を比較した臨床試験はない。
検査間隔についてのコンセンサスは得られていないが,病期0では4~5年毎,病期Ⅰでは2~5年毎,病期Ⅱでは2~3年毎,病期Ⅲでは6カ月~2年毎に行うことが推奨されている。病期Ⅳの高度異型腺腫または高密度腺腫などには,手術適応の評価あるいは6~12カ月毎の専門家によるサーベイランスが推奨される。病期Ⅳでは7~36%に癌化が認められるため,膵頭十二指腸切除術(pancreaticoduodenectomy:PD),幽門輪温存膵頭十二指腸切除術(pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy:PPPD)あるいは膵温存十二指腸切除術(pancreas-sparing duodenectomy:PSD)を考慮する。
術式について,PDやPPPDが選択されることが一般的だが,PSDに関しては1999年から2010年の間にデンマークのFAP13例に対しての報告がある。6例(46%)に術後合併症を認め,その内の3例は縫合不全であったが,保存的に軽快した。オランダからの報告では,1,066例のFAP患者のうち,43例に十二指腸切除が施行され(そのうち22例にPSD),1999年以降ではPSDが「予防的十二指腸切除」の第1選択術式となっている。しかしながら,本邦での実施は一部の施設に限られている。修正スピゲルマン病期分類に準じた十二指腸腺腫への対応の目安を図16に示す。
サイドメモ6
■スピゲルマン分類の評価法の変遷
スピゲルマン分類は1989年に提唱されたFAPに合併する十二指腸腺腫の病期分類である。腺腫の個数,最大径,組織構造,異型度について,各々1~3点が振り分けられ,合計点数から病期が決定される。2000年のVienna分類によって異型度がmild / moderate / severeの3段階からlow-grade/ high-gradeの2段階に変更されたため,low-gradeを1点,high-gradeを3点とする修正病期分類が提唱された。最近,NCCN guidelines(Genetic / Familial High-Risk Assessment:Colorectal V.2.2015)ではスピゲルマン分類ないし修正スピゲルマン分類を簡略化した分類が提案されている。この分類では病期0(腺腫なし),病期Ⅰ(1~4個の管状腺腫,1~4 mm大),病期Ⅱ(5~19個の管状腺腫,5~9 mm大),病期Ⅲ(20個以上あるいは1 cm以上の腺腫性病変),病期Ⅳ(腺腫が密生,あるいはhigh-grade adenoma)に分類されている。これらの病期分類を用いたサーベイランスや治療の妥当性について,前向き研究は行われておらず,今後の課題である。
CQ12:FAP患者の十二指腸乳頭部腫瘍(腺腫・癌)にはどのように対応するのか?
十二指腸乳頭部腫瘍に対する治療法の選択はその病態や臨床症状により,内視鏡的治療,手術療法が選択される。
十二指腸乳頭部腫瘍はFAP患者の50%程度に合併する。AFAPにも合併する。FAPにおける十二指腸乳頭部癌の一般集団に対する相対リスクは123.7倍と報告されている。内視鏡的乳頭切除術(endoscopic ampullectomy),あるいは十二指腸切開乳頭部局所切除術(transduodenal ampullectomy)は乳頭部に限局した腫瘍に適応となる。近年の内視鏡治療の進歩に伴い,前者が選択されることが多い。
乳頭部を含めた乳頭部近傍(2 cm以内)腺腫の焼灼除去は安全かつ有効とする報告,あるいは10年以上の長期観察で良性経過をとったので積極的治療は推奨されないとする報告がある。Maらは1990年から2010年に米国のFAP患者26例に対して行った内視鏡的乳頭切除術について遡及的に検討している。合併症として,膵炎(19.2%),腹痛(7.6%)および出血(3.8%)を挙げている。経過観察が可能であった24例中14例(58.3%)に局所再発を認めており,注意を喚起している。GluckらはFAP患者80例に対して,平均7.2年間の内視鏡的経過観察を行い,38例(47.5%)に乳頭部腫瘍を認めた。そのうちadvanced adenoma(腫瘍径10 mm以上,villous type,high-grade dysplasia)は10例で,超音波内視鏡検査(endoscopic ultrasnography:EUS)がその診断に重要であると報告している。また,15例に内視鏡的乳頭切除術が施行されたが,2例には再発病変に対して最終的に外科手術が行われた。手術に関して,内視鏡的治療が困難な乳頭部近傍病変を含む場合には膵温存十二指腸切除術(PSD)が,癌化が認められた場合には膵頭十二指腸切除術(PD)や幽門輪温存膵頭十二指腸切除術(PPPD)などが選択される。
CQ13:FAPの空・回腸病変にはどのように対応するのか?
小腸内視鏡検査やカプセル内視鏡検査が試みられているが,検査・治療に対するコンセンサスは得られていない。
空・回腸の腺腫はFAP患者の60~75%に発生する。カプセル内視鏡検査による検討では,十二指腸に腺腫を持つ患者では小腸にも腺腫が存在する傾向がある。腺腫の大きさは大部分が10 mm以下である。比較的多数例の検討によると,腺腫は空腸に数が多く回腸に少ない傾向がある。空・回腸癌の発生はまれなので,原則的に腺腫の内視鏡的摘除の適応はない。しかしながら,空・回腸の腺腫について,どのように検査を行い,治療すべきかについて未だ十分な検討はなく,今後の課題である。
CQ14:FAP患者のデスモイド腫瘍の治療方針は?
デスモイド腫瘍の治療法についてのコンセンサスは得られていない。発生部位や重症度に応じて,薬物療法,手術,保存的治療(経過観察)などが選択される。
デスモイド腫瘍に対する治療方針は,デスモイド腫瘍の特徴,治療法の種類,病期分類などを参考にして決定する。
1.特徴
デスモイド腫瘍は線維腫の一種で,転移はしないが浸潤性に発育する傾向がある。FAP患者の8~20%に認められ,腹腔内デスモイド腫瘍が全体の70%を占める。大腸切除後(特に2~3年以内)に,腹壁・腸間膜あるいは後腹膜に発生することが多く,腹腔内(後腹膜を含む)に発生した場合には,消化管通過障害,穿孔,膿瘍,あるいは尿管閉塞などの原因となり,しばしば治療に難渋する。デスモイド腫瘍が発生した場合の死亡率は0~14%と考えられる。
2.治療法の種類
デスモイド腫瘍の治療には,①自然消退ないし安定化があり得ること,②切除後の再発が10~68%にみられること,などの特徴を考慮する必要がある。治療として,薬物療法(化学療法を含む),外科治療,放射線治療などが報告されている。FAP患者のデスモイド腫瘍は,腸間膜発生など腸管に接する場合が多く,放射線治療は腸管障害をきたす可能性があるうえ,効果に乏しいので,一般的には推奨されない。
大きな,あるいは発育の早い腹腔内デスモイド腫瘍,あるいは腹壁デスモイド腫瘍にはNSAIDsの一つであるsulindac(300 mg/日)や抗エストロゲン薬のtamoxifen(40~120 mg/日)やtoremifene(180 mg/日)などが選択される。
Sulindacや抗エストロゲン薬は,腫瘍を縮小させる効果には乏しいものの,腫瘍の増大を抑える効果が報告されている。最近ではチロシンキナーゼ阻害薬であるimatinibの効果も検討されている。Desurmontらは36%の腫瘍縮小あるいは安定化が得られたと報告している。一方,Chughらは手術不能のデスモイド腫瘍に対し,1年の無増悪率が66%であるものの,腫瘍縮小はわずか3%と報告しており,現時点ではimatinibの効果は十分明らかとは言えない。
殺細胞性化学療法(cytotoxic chemotherapy)については,主にdoxorubicin(DOX)とdacarbazin(DTIC)の併用療法において高い奏効率が示されている。わが国でもDOX+DTIC療法の有効性が報告されている。DOX+DTIC療法以外では,methotrexate(MTX)とvinblastine(VBL)の有用性が報告されている。
Desurmontらは各種薬物療法ごとの腹腔内デスモイド腫瘍に対する奏効率を比較し報告している。殺細胞性抗がん薬77%,sulindac+tamoxifen 50%,tamoxifen 40%,imatinib 36%,sulindac 28%であることから,腹腔内デスモイド腫瘍に対しては,殺細胞性抗がん薬が最も奏効率が高く,治療の第1選択になりえるとしている。しかしながら,どのような腹腔内デスモイド腫瘍に対し,第1選択にすべきかということに関し,十分な検討は行われていない。
腹腔外デスモイド腫瘍切除後の再発率は高い(20~25%)が,術後合併症は少ない。切除後の再発の原因として,不完全切除だけでなく,切除創部に新生する場合も考えられるので,腫瘍辺縁の過剰な切除は控える。腹腔内デスモイド腫瘍による消化管通過障害には手術が考慮されるが,切除困難あるいは腸管大量切除が必要なため,手術が奏効しない場合がある。Smithらは完全切除例とバイパスを含む非切除例との間で生存率に差はないと報告している。
3.Churchの分類に基づいた腹腔内デスモイド腫瘍の治療
Churchらの分類を参考にして作成した腹腔内デスモイド腫瘍の病期分類を表5に示す。前向きな検討は行われていないが,病期Ⅰでは経過観察またはNSAIDs,病期Ⅱでは可能であれば手術およびNSAIDs+tamoxifen,病期ⅢではNSAIDs+tamoxifen+化学療法,病期Ⅳでは化学療法やバイパス手術などが選択肢となる(図17)。病期Ⅰ/Ⅱでは死亡例はなく,病期Ⅲ/Ⅳの死亡率はそれぞれ15%,44%と報告されている。尿管閉塞にはステント留置が推奨される。
CQ15:FAP患者において注意すべき消化管以外の悪性腫瘍は?
甲状腺癌,副腎癌,肝芽腫,脳腫瘍などが知られているが,甲状腺癌の報告が多い。これらの腫瘍に対するスクリーニング検査やサーベイランスの有用性については確認されていない。
FAP患者の1~6.1%に甲状腺癌が合併する。大部分が乳頭癌で,女性:男性=44:1と女性に好発する。女性患者では一般集団に対する甲状腺癌の相対リスクは23~160倍と報告されている。cribriform-morula variantという特徴的な組織像を呈することが多く,甲状腺癌が契機でFAPが診断されることもある。多発性,両側性の頻度がそれぞれ28.6~69%,42~67%と高いため,甲状腺全摘術を推奨する報告もあるが,FAPに合併した甲状腺乳頭癌の予後は良好であるため,術式の決定には慎重を要する。FAP患者の甲状腺癌に対するスクリーニングとして,触診に加えて超音波検査を推奨する報告がある。
FAP患者に脳腫瘍が合併する場合があることが知られている(ターコット症候群type 2)。女性は男性の2.4倍で,髄芽腫が最も多く(60%),星細胞腫,上皮腫なども報告されている。女性のFAPでは一般集団と比較して脳腫瘍全体では7倍,髄芽腫では92倍の相対リスクである。髄芽腫は小児期~若年成人に好発する。
FAP患者の7.4~13%に副腎腫瘍が合併する。一般集団に対する相対リスクは2.3~12.5倍とされている。CTで偶然発見されることが多い。Willらの30例の検討では,両側性が2例(6%)で,診断時年齢は26~69歳で,性差はなかった。ホルモン産生性腫瘍や悪性化が疑われる場合は手術適応となる。FAP患者の副腎悪性腫瘍の頻度は不明である。
FAPの小児の0.42~0.75%に肝芽腫が発生すると推定されている。3歳頃までが好発年齢で,一般集団に対する相対リスクは176~420倍以上とされている。診断は腹部超音波検査など画像検査で行われ,90%の患者でα-フェトプロテイン(AFP)高値がみられる。先天性網膜色素上皮肥大の併存が多くみられること,肝芽腫の家族歴を有するFAP家系では,発症リスクが高いことも知られている。治療は外科切除や化学療法が選択されるが,早期発見での完全切除後の予後は良好であることから,好発年齢時でのサーベイランスを推奨する報告がある。
CQ16:FAPの遺伝カウンセリングの注意点は?
FAP患者や未発症者を含む家族(血縁者)に対する遺伝カウンセリングの際には,FAPに関する情報提供,心理社会的支援を行う必要がある。
遺伝学的検査実施の有無にかかわらず遺伝カウンセリングを行う。遺伝学的検査の実施に際しては,日本医学会の「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(2011年2月),日本家族性腫瘍学会などのガイドライン,「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」などを遵守した上で,落ち着いて話せる時間と場所を確保し,医師が主体となって行う。
FAPの遺伝カウンセリングでは,50%の確率で遺伝し,APC遺伝子変異保持者は放置すればほぼ100%に大腸癌を発生することなどの当該疾患に関する情報提供とともに,選択肢の一つとしての遺伝学的検査の意義,方法,限界,費用などについて説明し,患者および家族が自立的選択を行えるように支援する。遺伝学的検査を受ける前後だけではなく,必要に応じて遺伝カウンセリングを継続して実施する。
FAPの血縁者に対する遺伝学的検査や診断的検査(下部消化管内視鏡検査)では,未成年者が対象となることが比較的多い。未成年者に対するこれらの検査を実施する上では,代諾者からの同意だけでなく,被験者の理解度に応じた説明を行い,本人の了解(インフォームド・アセント)を得ることが望ましい。
血縁者に対する遺伝学的検査では,同胞内で異なる結果(変異保持者と変異を保持していない者)となる場合がある。変異を受け継がなかったものが受け継いだものに対して「自分だけが助かってしまって申し訳ない」など自責の念(survivor guilt)を抱くことがあり,遺伝カウンセリングでは,変異を受け継がなかった家族に対しても心のケアが必要なことがある。
FAPでは発症する腫瘍や随伴病変も多岐にわたっており,複数の診療科との連携が必要になる。チーム医療として,社会的,経済的,心理的サポートを長期的に実施することが望まれる。
CQ17:リンチ症候群では原因遺伝子の種類によって関連腫瘍に対し異なる対応が必要か?
原因遺伝子の種類に応じて,関連腫瘍の発生リスクが大きく異なる場合がある。このため原因遺伝子の臓器別発がんリスクに応じたサーベイランスを行うことが提案されている。
主要な原因遺伝子であるMLH1変異例とMSH2変異例を比較すると,大腸癌のリスクはほぼ同等で,MSH2変異例では大腸以外の関連腫瘍のリスク(特に尿路系)が高いとする報告が多い。MSH6変異例の大腸癌発症リスクはMLH1やMSH2変異例と比較して低いが,子宮内膜癌のリスクはMLH1やMSH2変異例と同等またはそれ以上である(表10)。したがって,リンチ症候群では原因遺伝子別に関連腫瘍の発生頻度が大きく異なることに留意したサーベイランスを行うことが望ましい。しかし,日本人における原因遺伝子別の関連腫瘍発生リスクについては十分には調べられていない。
CQ18:大腸癌の病理組織学的所見のなかで,リンチ症候群の拾い上げに重要なものは何か?
腫瘍内リンパ球浸潤,髄様増殖,粘液癌・印環細胞癌様分化,クローン様リンパ球反応が散発性MSI-H大腸癌のみならず,リンチ症候群の拾い上げの参考になる。
MSI-H大腸癌は非MSI-H大腸癌と比べ,いくつかの組織学的特徴が有意に多く認められるため,これらの所見がリンチ症候群疑い患者の拾い上げに有用である。改訂ベセスダガイドラインにおいては,①腫瘍内リンパ球浸潤(tumor infiltrating lymphocytes:TIL),②髄様増殖,③粘液癌・印環細胞癌様分化,④クローン様リンパ球反応(Crohn’s-like lymphocytic reaction)の4項目が挙げられている(図24A,24B,24C,24D)。ただし,これらの組織学的特徴は必ずしもリンチ症候群に特有のものではなく,散発性MSI-H大腸癌にも共通して認められる。
CQ19:リンチ症候群(大腸癌未発症の変異保持者を含む)において,婦人科癌にどのように対応するか?
子宮内膜癌・卵巣癌に対するサーベイランス法は確立されていない。子宮内膜癌では子宮内膜細胞診または子宮内膜組織診,および経腟超音波断層法を行うことが専門家により提案されている。
リンチ症候群関連婦人科癌としては子宮内膜癌と卵巣癌がある。
子宮内膜癌はリンチ症候群において大腸癌に次いで2番目に高頻度のがんで,「センチネルがん」と位置付けられる。自覚症状として不正出血が最も頻度が高い。サーベイランス法には子宮内膜細胞診,子宮内膜組織診,経腟超音波断層法などがあり,病理学的検査で診断が確定する。なお通常の「婦人科がん検診」は子宮頸癌のスクリーニングを目的としており,子宮内膜癌や卵巣癌は念頭においていないことに留意する。
卵巣癌ではリスク低減手術が現時点で最も効果が高い1次予防法である。リスク低減手術を選択しなかった場合はサーベイランスを行うことになるが,その有用性は確立されていない。リンチ症候群と同様に卵巣癌を発症する遺伝性乳癌卵巣癌(hereditary breast and ovarian cancer:HBOC)症候群においても,経腟超音波断層法とCA125検査に関し,十分な感度および特異度は示されていない。実地臨床では6カ月に一度を目安として経腟超音波断層法とCA125検査を行うことが現実的な2次予防法である。しかし,前回の診察では陰性と判定されたにもかかわらず,次に予定された診察の前に自覚症状が出現してがんが発見される,いわゆるinterval cancerのリスクがある。
挙児希望がない,あるいは閉経後のリンチ症候群患者に対しては,がん一次予防法として子宮摘出術および両側卵管卵巣摘出術の選択肢の提示を考慮する。また大腸癌発症者においては大腸癌の手術時に子宮・卵巣を同時に摘出するというオプションを示すことができる。リスク低減手術の実施には,倫理審査委員会の承認や診療体制について,事前に十分検討する必要がある。
リスク低減手術を希望せずサーベイランスを選択する患者に対しては,表9(④術後のサーベイランス)を目安にする。
CQ20:リンチ症候群のスクリーニング検査(MSI検査と免疫染色)において,どのような点に注意するのか?
どちらの検査も感度・特異度は同等で,免疫染色では原因遺伝子の推定が可能である。コストや利便性は施設ごとに異なるので,総合的に判断してどちらか一方の検査を選択すればよい。
リンチ症候群の大腸癌の90%以上にMSI-Hを認めることが報告されている。一方,大腸癌全体に対するMSI-Hの割合は,欧米の報告では12~16%,わが国の報告では6~7%である。そのため,MSI検査はリンチ症候群を疑う症例を絞り込むスクリーニング検査として有用である。MSI検査は,リンチ症候群が疑われる大腸癌症例を対象とする悪性腫瘍遺伝子検査として平成18年度より保険収載されたが,検査の実施に際しては遺伝性のがんである可能性について,十分な説明と同意が必要である。日本家族性腫瘍学会ホームページ(http://jsft.umin.jp/)のリンク先に参考資料が公開されている。
MSI検査で注意すべき点として,MSH6遺伝子に生殖細胞系列変異があるリンチ症候群では,MSI-Hを示さないことがある。したがって,MSI-L,MSSであってもアムステルダム基準Ⅱを満たしている場合やリンチ症候群を強く疑う臨床的特徴(若年発症や多重がんなど)が認められる場合は,ミスマッチ修復遺伝子の遺伝学的検査を考慮する。近年,広まりつつある1塩基の繰り返しのマーカー(mononucleotide repeat marker)を主体としたMSI検査ではMSH6変異例の感度も高いとされている(サイドメモ9:MSI検査の方法と結果の評価)。
一方,ミスマッチ修復タンパクに対する免疫染色がリンチ症候群の2次スクリーニングとして急速に普及しつつある。免疫染色は多くの施設で実施可能である。また,検査の実施に際してはMSI検査同様十分な説明と同意が必要である。日本家族性腫瘍学会ホームページ(http://jsft.umin.jp/)のリンク先に参考資料が公開されている。
MSI検査と免疫染色は手法が異なるが,どちらの検査も感度・特異度は同等で,免疫染色では原因となる4種類の遺伝子の推定が可能である。各々の検査のコストや利便性は施設ごとに異なるので,施設の検査体制も加味して総合的に判断し,どちらか一方の検査を選択すればよい。しかし,一方の検査が陰性であっても臨床的にリンチ症候群が疑わしい場合には,もう一方の検査を行うことで補完的な拾い上げが可能となる。
サイドメモ9
■MSI検査の方法と結果の評価
MSI検査は複数の臨床検査会社で実施されている。MSI検査には腫瘍部および非腫瘍部正常組織の凍結材料またはホルマリン固定パラフィン包埋標本が必要である(正常組織のかわりに血液検体を用いてもよい)。抽出したDNAから,マイクロサテライトの長さについて,腫瘍組織と正常組織で比較する。MSIの判定には一般的に,5種類のマーカー(ベセスダマーカーあるいはNCI panelとして知られている。1塩基の繰り返しマーカー2種類と,2塩基の繰り返しマーカー3種類からなる)を用いて行われてきた(Step 2 第2次スクリーニングで行う検査)。さらに多数のマーカーを用い,30%以上のマーカーで腫瘍部のマイクロサテライト長の変化が認められる場合にMSI-Hとする場合もある。また,1塩基の繰り返しのマーカー(mononucleotide repeat marker)の感度が高いことから,3つ以上のマーカーを用いて,不安定性があればMSI-Hとする考え方もある。Mononucleotide repeat markerによるMSI検査は腫瘍組織のみで解析可能なものがあり,わが国でも急速に普及している。
CQ21:ミスマッチ修復遺伝子産物(タンパク)の免疫染色における評価ポイントは?
細胞核のミスマッチ修復タンパクの消失パターンから,ミスマッチ修復異常の原因となる遺伝子を推定可能である。染色評価にあたっては内部陽性対照を用いて染色の適切性を確認しておく。
1.内部陽性対照
ミスマッチ修復タンパクは核に局在し,増殖細胞により強く発現する。非腫瘍組織では大腸粘膜の腺底部やリンパ濾胞の胚中心がよい陽性コントロールになる(図25)。腫瘍組織は一般に増殖活性が高いため,内部陽性コントロールの染色が確認できれば判定は容易なことが多い。
2.染色のパターンと評価
ミスマッチ修復異常のない腫瘍では4種類のタンパク全てが発現している。ミスマッチ修復異常を呈する腫瘍では異常のあるミスマッチ修復遺伝子を反映したタンパクの発現消失を呈するが,個々のミスマッチ修復遺伝子異常とタンパクの発現消失は1対1対応にならない(表11,図26)。大半の症例は表11に当てはまる染色パターンを示す。表11に当てはまらない染色結果を得た場合は,例外的な症例である可能性を考慮する前に染色の妥当性を確認すべきである。浸潤がんの場合,原則として発現消失はびまん性である。
MLH1変異腫瘍はMLH1に加えてPMS2,MSH2変異腫瘍はMSH2に加えてMSH6の発現消失を伴うため(表11),PMS2,MSH6に対する2種類の抗体のみで4抗体を用いた場合と同等の感度でリンチ症候群のスクリーニングを行うことが可能である。PMS2の発現消失が認められた場合はMLH1の染色を,MSH6の発現消失が認められた場合はMSH2の染色をそれぞれ追加し,変異遺伝子の推定を行う。
サイドメモ10
例外的な染色結果
■ミスセンス変異などによる異常タンパクの発現
ミスセンス変異(付録:Ⅱ.ゲノムバリアントの記載法 3. 変化の種類)の場合,機能が保たれていないタンパクが発現することがある。MLH1変異を伴うリンチ症候群に比較的多いことが知られており,これらの症例の大半はPMS2の単独発現消失を呈する。ただし,免疫染色で異常が全く指摘できない例がまれに存在する。免疫染色で異常が認められなくても臨床的にリンチ症候群が強く疑われる場合は,MSI検査を追加することで拾い上げが可能となることがある。
■マイクロサテライト不安定性によるミスマッチ修復遺伝子の2次的変異
ミスマッチ修復遺伝子のいくつかには繰り返し配列を持つものがあり,2次的な変異を起こすことがある。MLH1遺伝子変異(MLH1 / PMS2消失)例では,びまん性または領域性にMSH6の発現消失をきたすことがある。
■術前化学放射線療法によるMSH6の発現消失
術前化学放射線療法を行った場合,MSH6に異常がなくてもMSH6の発現消失を示すことが報告されている。
CQ22:リンチ症候群の遺伝子診断の意義と注意点は?
リンチ症候群の確定診断にはミスマッチ修復遺伝子に対する遺伝学的検査が必要である。遺伝学的検査の対象者を選択し,遺伝カウンセリングを行い,検査を受けるかどうかの意思を確認する。遺伝学的検査の結果を評価し,血縁者の遺伝子診断や本人,血縁者の医学的管理などの対応に役立てる。
リンチ症候群の確定診断にはミスマッチ修復遺伝子の生殖細胞系列変異を同定する必要がある。遺伝学的検査の対象者(患者・血縁者)を適切に選別し,遺伝学的検査の前後に必ず遺伝カウンセリングを行う。遺伝学的検査を行ってもリンチ症候群が確定できない症例もあり,結果の解釈は慎重に行う。ミスマッチ修復遺伝子の検査は保険収載されていないが,検査会社に依頼することができる。
1.ミスマッチ修復遺伝子の遺伝学的検査
遺伝学的検査を実施する前後には,遺伝性疾患特有の注意点や配慮すべき点があるので,遺伝カウンセリングを実施する。遺伝学的検査に関する説明は,原則として医師が行うが,遺伝カウンセリングを実施している施設に紹介してもよい。遺伝学的検査実施の同意が得られた場合には,約2~3 mLの採血を行い,遺伝学的検査を実施している検査会社に依頼する。解析方法は一般にダイレクトシークエンス法であるが,変異が見つからない場合,遺伝子の一部が大きく欠損・重複するか,再構成している可能性があり,MLPA(multiplex ligation-dependent probe amplification)法やサザンブロット法などを用いて解析する。
2.遺伝学的検査結果の評価
明らかな病因となる遺伝子変異が見つかれば,リンチ症候群が確定する。遺伝学的検査結果開示後は,遺伝カウンセリングや今後のサーベイランスの計画・実施,血縁者の遺伝学的検査などを検討する。一方,遺伝子に変異が見つかっても疾患との因果関係が不明(variant of uncertain significance:VUS)なケースもある(CQ23)。その場合は,遺伝学的検査を行わなかった状況と同じと考え,その後のサーベイランスを行う。遺伝学的検査で変異が見つからなかった場合,現在の検査法では検出できない遺伝子変化である可能性や未知の原因遺伝子が存在するなどの可能性が残るので,リンチ症候群が完全に否定されるわけではない。既往歴・家族歴に応じてリスクを評価し,必要なサーベイランスを行う。発端者の遺伝学的検査を行っても変異が見つからなかった場合は,その他の血縁者の遺伝学的検査(遺伝子診断)を実施する意義は乏しい。
3.血縁者の遺伝学的検査
発端者に明らかな遺伝子変異が見つかれば,血縁者が同じ遺伝子変異を持つかどうかを確認することができる。その場合,変異が見つかった領域のみを検査する。血縁者の遺伝学的検査の前後にも,遺伝カウンセリングが必要である。原因遺伝子の変異が見つかれば今後のサーベイランスの計画・実施へと結びつけることができる。遺伝学的検査を受ける時期としては,がんの若年(10歳代,20歳代)発症の家族歴がない限り,一般的には成人になってからである。自分の意思で遺伝学的検査を受けるかどうかを決定する。
大腸癌研究会の多施設共同研究では,リンチ症候群の第1度近親者の死因として欧米で多い大腸癌,子宮(内膜)癌以外に,日本人では胃癌,卵巣癌,胆道癌などのリンチ症候群関連腫瘍が上位を占めていた。リンチ症候群が確定した近親者にはこれらの悪性腫瘍を念頭に入れたサーベイランスが重要である。
CQ23:リンチ症候群の遺伝学的検査における「病的か意義不明なバリアント」(variant of uncertain significance:VUS)にはどのように対応したらよいか?
遺伝学的検査を行わなかったときと同じように対応する(図22)。可能であれば,血縁者に対してバリアントの有無の検査を実施し,腫瘍の発症との関連を検討する。
遺伝学的検査のなかには,「病的か不明(意義不明)なバリアント(VUS)」との結果が得られることがある。VUSの臨床的意義の解釈は,データベースの更新などに伴って変更されることがある。バリアントのタンパク機能に対する影響について予測するプログラム(Sorting Intolerant From Tolerant:SIFT http://sift.jcvi.org/index.html,Polymorphism Phenotyping version 2:PolyPhen-2 http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2など)がある。血縁者におけるこのバリアントの有無と腫瘍発生に強い関連がある場合や,免疫染色におけるミスマッチ修復タンパクの消失パターンがVUSを認めた遺伝子と一致する場合などでは病的変異の可能性が高まるが,その判定には十分な検証が必要である。
確定する情報が得られない場合は以下のように対応する。
- 腫瘍がMSI-Hまたは免疫染色でミスマッチ修復タンパクの消失を示す症例が,臨床的にもリンチ症候群の特徴を認める場合には,リンチ症候群とみなして対応する。
- 腫瘍がMSI-Hまたは免疫染色でミスマッチ修復タンパクの消失を示す症例が,臨床的にリンチ症候群を疑う所見を持たない場合には,家族歴・既往歴をもとに定期的な観察を継続する。
CQ24:リンチ症候群の遺伝カウンセリングを行う際のポイントは?
リンチ症候群が疑われる患者および家族(血縁者)に遺伝カウンセリングを行う際には,リンチ症候群の概要,遺伝形式,診断に必要な検査,大腸癌を含めた関連腫瘍のリスクとサーベイランスなどの説明,疾患に関する情報資源の提供,心理社会的支援などを行う。
リンチ症候群の遺伝カウンセリングでは,以下の(1)~(4)の内容に留意して実施することが重要である。
(1)個人の既往歴や家族歴の聴取を行う。
(2)以下に示すような情報を提供する。
リンチ症候群の概要(臨床症状,浸透率,自然経過,頻度,原因遺伝子,診断,治療,予防など),遺伝形式(常染色体優性遺伝),個人(とその血縁者)のがんのリスク,遺伝子変異が見つかる可能性,病的変異があった場合の各種がんのリスク,リンチ症候群関連検査(MSI検査,免疫染色,ミスマッチ修復遺伝子診断など)の概要,リスクに基づく予防策(特に検診サーベイランス),インターネットや書籍などの情報資源,当事者団体情報,国内外の研究の状況
(3)リスクに応じた関連腫瘍のサーベイランスを提示する。
(4)心理社会的支援を行う(疾患に対する心配や不安,家族間の軋轢などについて傾聴し,共感的理解を示す)。
CQ25:リンチ症候群の大腸癌に対する術式選択は?
散発性大腸癌と同じ術式か,リンチ症候群の大腸多発癌のリスクを考慮し拡大手術を行うべきかについてのコンセンサスは得られていない。
リンチ症候群の大腸癌に関する後方視的コホート研究では,大腸部分切除(segmental resection)後の異時性大腸癌の累積発生率は10年:16%,20年:41%,30年:62%であり,切除する腸管が長くなるにつれて異時性大腸癌のリスクは減少することが報告されている。
また,リンチ症候群の初発大腸癌の15%程度が直腸癌であるが,直腸切除(切断)術を施行された症例における異時性大腸癌は,ほとんどが右側結腸癌で,平均14カ月間隔で内視鏡サーベイランスを行った場合の異時性多発大腸癌の累積発生率は,10年:19%,20年:47%,30年:69%とする後方視的コホート研究がある。直腸癌が初発の場合に,大腸全摘術を選択するかどうかのデータは乏しい。
ミスマッチ修復遺伝子に異常があると診断され,未だ大腸癌に罹患していない変異保持者に予防的大腸切除を行うか否かについてもコンセンサスは得られていない。リンチ症候群の大腸癌の生涯発生リスクは男性で54~74%,女性で30~52%であり(表6),生涯を通じて大腸癌を発生しない変異保持者が少なからず存在することから,FAPのように一律に予防的大腸切除を勧めることはできない。したがって,リンチ症候群の異時性大腸癌のリスク,サーベイランスの必要性とその限界,予防的切除の意義,術後のQOLなどを変異保持者に説明し,変異保持者自身が対応を決定するのが望ましい。
CQ26-1:リンチ症候群の大腸癌に対する有効な補助化学療法は?
リンチ症候群の大腸癌に限定した術後補助化学療法の有効性について明らかなエビエンスはない。リンチ症候群のStageⅢ結腸癌(大腸癌)は,術後補助化学療法の適応となりうる。
リンチ症候群の大腸癌について,特異的な化学療法のエビデンスはほとんどないため,MSI-Hを示す散発性大腸癌に準じて考えられる場合が多い。しかし,5-FUベースの術後補助化学療法が,MSI-Hを示す散発性大腸癌には有用性がないが,リンチ症候群が疑われる50歳未満のMSI-H大腸癌においては有用性があるとする報告もあり,MSI-Hを示す散発性大腸癌とリンチ症候群の大腸癌を別に考える必要性も示唆されている。なお,散発性MSI-Hあるいはリンチ症候群の直腸癌に対する術後補助化学療法に関する有用なデータはほとんどない。
StageⅡ /Ⅲの散発性大腸癌を対象に,MSIの状態と5-FUを含む術後補助化学療法の有効性について行われたメタアナリシスでは,MSI-H大腸癌はMSS大腸癌より予後は良いが,術後補助化学療法により生存期間および無再発生存期間の改善が認められなかった。しかし,NSABP-C07試験,MOSAIC試験において,術後補助療法におけるオキサリプラチンの上乗せ効果はMSI-H,MSS結腸癌のいずれにも認められた。したがって,現状ではStageⅢ結腸癌においてMSIの状態により術後補助療法の適応を判断することは推奨されない。StageⅡ大腸癌における術後補助療法の有用性は確立されておらず,特にMSI-Hの場合は予後良好であるため,その有用性が低いと考えられている。
CQ26-2:リンチ症候群の進行・再発大腸癌に対する有効な化学療法の選択は?
リンチ症候群の進行・再発大腸癌に限定した化学療法の有効性について明らかなエビエンスはない。一般の大腸癌と同じ治療方針を選択する。
Stage Ⅳの散発性大腸癌においてはStageⅡ /Ⅲに比べてMSI-Hを示す頻度が低いことが示されている。リンチ症候群あるいはMSI-Hを示す進行・再発大腸癌に特異的な化学療法に関し,十分な検討は行われておらず結論は得られていない。したがって,散発性大腸癌に一般的に選択されるレジメンが適応となり得る。なお,散発性MSI-H大腸癌において,5-FUに抵抗性となった後の2次治療としてのイリノテカンの奏効率がMSI-Hの場合に有意に良好であるとする報告がある。最近の免疫チェックポイント阻害薬に関する報告が注目されている(サイドメモ11:MSI-Hを示す腫瘍と抗PD-1抗体薬)。
サイドメモ11
■MSI-Hを示す腫瘍と抗PD-1抗体薬
近年,進行・再発大腸癌において,免疫チェックポイント阻害薬である抗PD-1抗体がMSI-Hを示す場合に特に有効であることが示され,リンチ症候群の大腸癌でも有効性が期待される。奏効率はMSI-H大腸癌(40%)およびMSI-Hを示す大腸癌以外の癌(71%)においてMSS大腸癌(0%)より有意に良好であった。ただし,MSI-Hを示す癌のうちリンチ症候群とされる11例のサブグループにおいては奏効率が27%であり,散発性MSI-Hを示す癌よりは低かった。いずれにしてもリンチ症候群を含め,MSI-Hを示す癌に対する薬物療法が大きく変わる可能性が示された。
CQ27:リンチ症候群の発がんに対する有効な生活習慣の改善策は?
リンチ症候群の大腸発がんに対し,禁煙や適切な体脂肪のコントロールが推奨される。
喫煙,体脂肪(body mass index),アルコール消費,食事(赤身肉,加工肉,野菜,果物,魚,乳製品,食物繊維)などに関する検討がなされてきた。喫煙と体脂肪に関しては,発がんと関連性があるとする前向きコホート研究を含んだ複数の報告がある。
大腸癌研究会の多施設共同研究の結果から,喫煙はリンチ症候群の同時性・異時性大腸多発癌のリスク因子になることが示唆されている。
現時点のエビデンスから,リンチ症候群の大腸発がんに対し,禁煙や適切な体脂肪のコントロールが推奨される。
CQ28:リンチ症候群の発がんに対する有効な化学予防の方法は?
アスピリンがリンチ症候群の関連腫瘍の発生を抑制する可能性がある。
CAPP2試験はリンチ症候群の関連腫瘍と大腸腺腫の発生率に関し,アスピリンの予防効果を2重盲検で評価した初めての試験である。長期間の経過観察の結果,primary endpointの大腸癌の発生とsecondary endpointの大腸癌以外のリンチ症候群関連腫瘍の発生について,有意な予防効果が示された。大腸腺腫の発生予防については有用なデータが得られなかった。この試験におけるアスピリンの用量は600 mg/日であり,欧米人に比べてアスピリンの胃腸障害に弱い人種である日本人には使用が困難と推測される。一方,後方視的研究ではあるが,リンチ症候群を対象としたアスピリンやイブプロフェンの大腸癌予防効果を示す検討症例数の多い報告もある。用量や服用期間などが今後の検討課題として残されている。低用量アスピリンが散発性大腸癌の発生を抑制するとの報告は多いが,リンチ症候群においては臨床試験が進行中である。
CQ29:リンチ症候群の患者に対する大腸内視鏡によるサーベイランスは有効か?
リンチ症候群における内視鏡サーベイランスと腺腫の摘除は大腸癌の発生と死亡を減少させる。
リンチ症候群では,大腸癌の術後で大腸が残存している例を含め大腸癌の発生リスクが高いことが示されており,前癌病変である腺腫の摘除と大腸癌の早期発見を目的とした定期的かつ生涯にわたる内視鏡サーベイランスが必要である。サーベイランスの開始年齢は,20~25歳を推奨する報告が多い。検査の間隔に関しては,Järvinenらの前向き研究で,3年間隔の内視鏡サーベイランスにより大腸癌による死亡が65%抑制されることが報告された。しかし,いくつかの観察研究で3年毎の内視鏡検査の間に進行癌の発生が確認されたことから,検査間隔を1年とする報告も多い。
リンチ症候群の大腸腺腫は,若年(40歳未満)発症で,MSI-Hを示すことがあり,通常の腺腫より小さくても異型度が高く,癌化までの期間が短いと考えられる。また大腸腺腫の生涯累積発生数は約20個程度までと報告されている。したがって,腫瘍性病変の発見時には大きさに関わらず積極的な内視鏡的摘除の対象とする。